医療から灌漑事業へ
日本人にとっては物理的のみならず本当に遠い山の国、アフガニスタン。ユーラシア大陸の中央に位置し、年間の降水量は日本の5~10分の1だ。昔から「民族の十字路」と呼ばれてきたように多様な民族で構成され、地縁と血縁を尊重する人々が暮らしてきた。荒野のイメージが強いが、かつては農業が盛んで、自給自足の農業立国だったという。しかし、長年の紛争と旱魃で瀕死の状態が続いている。彼の地で、何度も苦難に見舞われながらも35年に渡って「人としての倫理の普遍性」を信じて人・自然と共に生きてきた作者は2019年12月4日、何者かの銃撃を受け、天に召された。
この本は、そんな作者が自身の行ってきた医療・灌漑事業を現場の視点で振り返った記録である。幼少期を北九州で過ごした彼は、祖母マンと作家の伯父、火野葦平の影響を強く受けて育った。マンは日ごろから「弱者は率先してかばうべきこと、職業に貴賤のないこと、どんな小さな生き物の命でも尊ぶこと」などを繰り返し説いていたという。芥川賞作家の伯父は戦時中に「兵隊三部作」を執筆し、爆発的な人気を博したものの、戦後は戦争の意味を問い続け、自決してしまった。
昆虫好きだった少年は成長し、九州大学医学部に進学、精神科医となったが、日本キリスト教海外医療協力会から声がかかり、1984年から90年まで、パキスタン北西部のペシャワールにある病院で働いた。ハンセン病患者の治療に当たっていた中村はそこで、ソ連軍の侵攻で混乱するアフガニスタンから国境を越えてやってきた患者に出会い、アフガニスタンで診療所を開設することを決意した。
戦闘の激化などに苛まされながらも、着々と準備を進め1991年1月から、アフガニスタン北東部の山村無医地区に診療所を開設していった。しかし、2000年春、未曽有の旱魃にさらされ、農民たちは続々と村を捨て流民化。診療所には、餓死しかけた幼児を抱いた母親が目立って増えたという。「もう病気治療どころではない」と、診療所のスタッフが村人と一緒に井戸を掘る作業を開始し、2006年までに約1600ヶ所で井戸を掘った。だが、飲料水があるだけでは生活はできない。元来の農村の復活こそ健康と平和の基礎だと考え、沙漠化した田畑の回復が新たな目標となった。数学が苦手だった中村は高校生の娘から教科書を借りて学習し、流水計算など灌漑事業に必要な知識を身に着けた。途中、日本人スタッフの“殉職”などの試練もあったが、専門家や地元の人々の協力を得て、2009年8月には約24キロの用水路が開通し、農村が復活した。
聖人の匂いはしないが、重い中村の言葉
沙漠に出現した緑の世界を中村は「樹間をくぐる心地よい風がそよぎ、小鳥がさえずり、遠くでカエルの合唱が聞こえる。・・・騒々しいアフガン情勢とはまるで別世界だ。・・・ここは、もはや沙漠ではない」と描写する。
中村はなぜ、ほとんど縁もゆかりもなかった異国の地で、このように生きることができたのだろうか。本書は、灌漑に関する専門的記述も多いが、数々の胸を打つ言葉が光を放っている。現場で実務に携わり、試行錯誤を繰り返しながら前に進んできた経験を持つ者のみが、生み出せる言葉だ。「私たちが己の分限を知り、誠実である限り、天の恵みと人のまごころは信頼に足る」、「平和とは観念ではなく、実態である」、「自然は制御できない。恩恵は自然と和してこそ褒美として与えられる」。中村の言葉からは、噓臭さも崇高さを追究する聖人の匂いもしない。
翻って、近年、SNSなどのメディアに氾濫する言葉の何と空しいことか。もちろん、私の言葉も実のあるものとは言い難い。ただ、一歩でも彼に近づけるのように生きていこうと思う。とはいえ、中村はこの本を上梓してから約6年後に、慈しんできた地で殺害されてしまった。彼岸に渡った彼はいま、何を思うのだろうか。


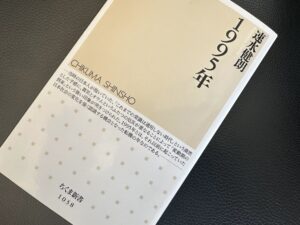
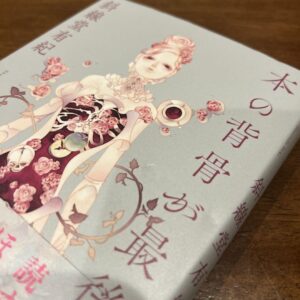
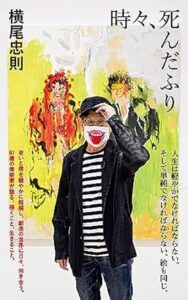
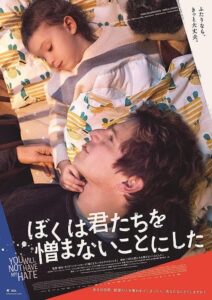
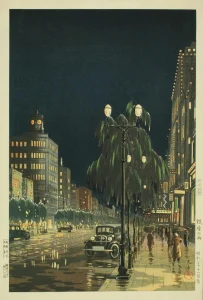
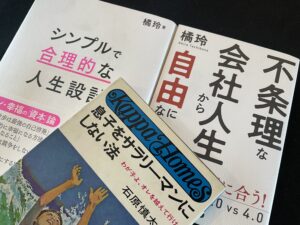
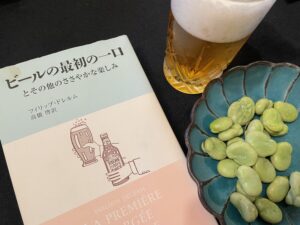
コメント