ミスティック・リバー (2004年) 出演:ショーンペーン、ティムロビンソン、ケビンベーコン
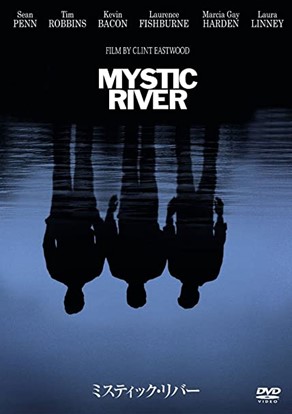
スタンドバイミーたちのその後
ミスティック川が流れるボストン郊外の労働者階級の街、イーストバッキンガムが舞台。幼馴染だった街に住む3人の男たちが、若い娘の殺人事件を契機に再会する。一人は刑事として、一人は被害者の娘の父として、そしてもう一人はその容疑者として。“もうひとつの『スタンドバイミー』を見るため、あなたは大人になった”と当時の宣伝文句にあるように、この殺人事件の25年前、彼らの少年時代の誘拐事件が物語の伏線の中心となっている。鮮やかな街の空と川の色彩、暗く陰鬱な街と森の夜のシーンは静謐さをもって映画全体を覆い、視覚的な対比が物語の明暗と相まって劇的な効果を生み出し、物語が静謐にかつ大きく動いていく暗示となっている。物語は、友情、裏切り、後悔、罪悪感、復讐といった様々な感情が交差し、じわじわと観る者を攻めてくる。そして、犠牲者の家族や友人、そして捜査官たちの複雑な心情を描き出し、終幕になって観客に深く静謐な感情を呼び起こす。現時点では、クリント・イーストウッド監督の代表作と断言できる、極めて完成度の高い作品だ。この年のアカデミー賞、作品賞と監督賞は『ロードオブザリング 王の帰還』に授けられたが、ショーンペーンが主演男優賞、ティム・ロビンスが助演男優賞をそれぞれ獲得した。
チェンジリング (2008年) 主演 アンジェリーナジョリー
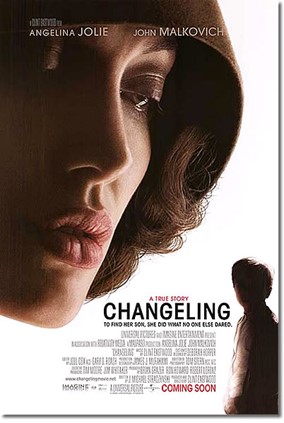
わが子への母の強い愛
True Storyというシンプルな文字が冒頭に映し出される。この一言がこの物語を最後まで貫いていく。嘘のような話が次々から次へと展開されていく。True Storyという前提を胸に抱きながら、そのありえない話が確固たるリアリティで私たちに向かってきて、観る者を掴んで離さない。舞台は1920年代のロサンゼルス。アンジェリーナジョリー演ずるシングルマザーが職場に出ている間幼い息子が行方不明になる。そしてその数ヶ月後、ロサンゼルスから3千キロも離れたイリノイ州で息子は発見される。母親の元に戻された息子。大勢のマスコミの前、感動の再会を予期していたが、シングルマザーの一言に愕然とさせられる「この子は私の息子ではない」。しかし、シングルマザーは警察や市の役人たちに圧力をかけられ、息子として受け入れなければと、精神病院に入れられてしまう。この状況下、彼女は息子を探すために一人で闘い、やがて真実が明らかになっていくというストーリー。この映画は、当時のロス市警の汚職や、社会的な問題を描き、人権問題や倫理的な問題について考えさせられる作品として高い評価がされたが、何より圧倒的なのは我が息子を見つめる母親の眼差しと思いを演じたアンジェリーナジョリーの馬力ある演技だ。母親の愛情、女性の強さを画面全面に出し、最後まで引っ張っていく演技によって、もうひとつのTrue Storyが完結する。これまでどちらかというと女性を描くのが得意でなかったイーストウッド監督が新境地を開拓した作品となった。
グラントリノ (2008年)
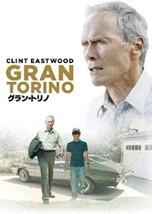
礼節による人生のリセット、そして『東京物語』
クリント・イーストウッド演ずる主人公のウォルト・コワルスキーは、朝鮮戦争の退役軍人で、フォードの自動車工場労働者でもあった。妻を亡くした葬儀のシーンから映画は始まる。 既視感のある葬儀の風景だった。2人の息子たちとその家族ともも疎遠になり、独りでミシガン州デトロイトに住んでいる。退役軍人故の厳格な信条を持ち、ビールと煙草をこよなく愛している。ウォルトは2台のフォード車を持っている。1台は70年代の黄金期の象徴でもある、映画のタイトルのグラン・トリノ・スポーツ・ファストバック。もう一台はフルサイズのピックアップのF-150で、アメリカの自動車産業における競争力を象徴し、アメリカの道路を走る自動車のアイコンだ。
冒頭のシーンから眉間に皺をよせ、物静かで無表情で街や世間を眺めながら人を寄せ付けないウォルト。そして人種差別的な偏見をもち、唾を吐きながら「クロ」「イエロー」を連発するアメリカ老人のステレオタイプだ。肉体的、精神的にもアメリカ仕様のタフな老人だ。読んでいた新聞の占い欄のコメント「やり直すなら今」を彼が声に出した何気ないシーンから、この後ウォルトがどう変化していくかを私たちは眺めていくことになる。人種差別の偏見の克服は予見できるが、朝鮮戦争で犯した自らの行為の告白やギャング団の襲来、自身の体を蝕む病魔等、いくつもの伏線が重っていく中で、自らの過去や人生に向き合い、老いてからも成長を遂げる姿が描かれ、老いに対する考え方や人生観にも深い示唆を与えてくれる。「退役軍人としての道徳観念」と評していたコメントが多かったが、違うと思う。「人としての礼節」をウォルトが最後になって行動したからだ。冒頭の葬儀のシーンの既視感は小津安二郎『東京物語』の終盤、笠智衆演ずる平山周吉の妻トミの葬儀後の空間そのものではないか。『東京物語』には家族関係を通して「人としての礼節」が描かれていた。『グラントリノ』は『東京物語』へのオマージュであるかもしれない。

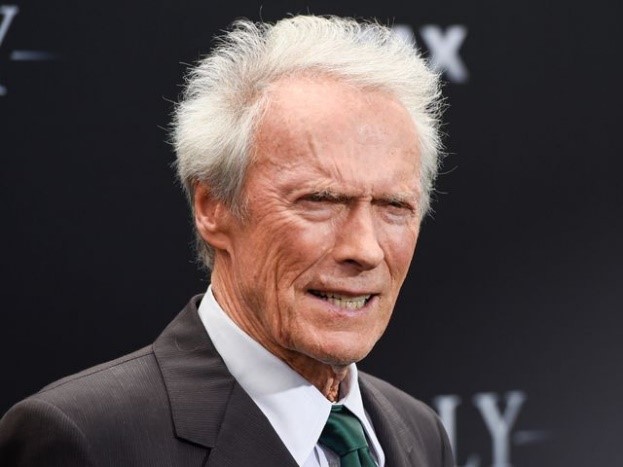




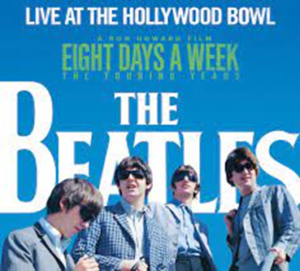
コメント