『変なおじさん』志村けん著

志村けんさんが亡くなられて1年が過ぎた。昨年の訃報の際は、コロナ禍第一波の渦中だった。彼の死は、その悲しさと併せてウィルスの猛威の象徴としても連日扱われていた。自身の筆による『変なおじさん』再読。小さな笑いをとるために、アンテナを立て周囲を見渡し、日常生活の景色を紡ぐといった精密な計算を尽している志村けんさんの思考回路が克明に伺える。志村さんの生来持っていた繊細な性格と、ドリフターズのリーダーいかりや長介の「台本を練り込む」仕事のスタイルが彼の頭と体に組み込まれていく過程がわかる。1974年(昭和49年)荒井注の後任としてドリフの新メンバーになった志村さんは舞台の裾の端から端を、ただ走っていただけの長髪の見習いの男だった。私を含め同級生たちは、ブルース・リーの物真似をしながら舞台を疾走する、同じ見習いだった、すわしんじを推していたのを思い出す。舞台に立ってから2年後、少年少女合唱隊での東村山音頭でブレイクしてからは、加藤茶氏とツートップでドリフを牽引していく。ブレイクするまでの2年間、毎週舞台から笑いの取れない自身の演技を冷静に分析している姿と、そこでの苦労がその後一気に開花していく熱いスピード感が交差していく。
いかりや長介氏の著書『だめだこりゃ』には「今思えば、この志村だけが本格的なコメディアンの才能を備えていた」「他の付き人とは違い、貪欲に笑いを盗もうとしていたし、作ろうとしていた。」「ちょっとした空き時間にネタを見てくれなんて発表していたのは志村だけだった。」と志村さんのことを評している。入門して付き人時代からの彼のお笑いに向き合う真摯な姿勢から、荒井注さんの代役は志村さんしかいなかったことがよくわかるエピソードだ。

常日頃から突き詰めて笑いの研究をし、行きついた結論が、お笑いは老幼男女に分かるように、ただの言葉だけではない、といった境地に向かう。「カラスの勝手でしょ」「アイ~ン」「最初はグー」「だいじょうぶだぁ」「マダムヤーン」「変なおじさん」一見、支離滅裂なギャグが、極めて精緻な世の中の観察とそこから導き出させる論理からのシンプルなアウトプットになる過程は、優れた思考回路を解説しているドキュメンタリー映像を眺めている気がしてくる。アウトプットまでのひとつひとつの過程は志村さんが喜劇王になるまでの階段でもある。
きちんと計算して笑わせるコントは得意だけど、アドリブが苦手との冷静な自己分析をもしている。だからだろう、トーク番組での姿は記憶にない。一周忌を追悼する各TV番組やyoutubeには、ひたすらお笑いに徹する志村さんの姿が流されていた。何度観ても笑えるから、もはや古典の域に達している。「ケンちゃん、お笑いはバカになりきることだよ。いくらバカをやっていても、見る人はわかっている。自分は文化人だ、常識があるんだってことを見せようとした瞬間、コメディアンは終わりだよ。」東八郎氏から志村さんが授かったというこの言葉を大事にしていたという。文字通り、生き様となった。 (2023.5加筆修正)








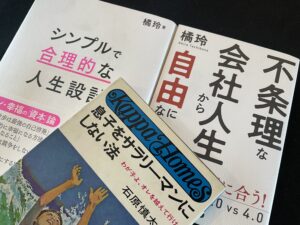
コメント