速水健朗著「1995年」
1995年は、地下鉄サリン事件、阪神・淡路大震災、オウム真理教事件など日本社会に大きな衝撃を与えた出来事が相次いだ年。同時代を生きた身として察するに1995年は「戦後史の転機」として捉えることができる。その意味を多角的に考察できる、「超・日本現代史」。一読後、同世代と一献交えながら語りたくなる。
政治と経済の視点から。
1995年は、戦後50年という節目の年であり、同時に政治体制の転換期でもあった。自民党55年体制が崩壊し、村山富市を首班とする初の社会党・新党さきがけ連立政権が誕生。この政権は、政治改革や経済活性化などの課題に取り組んだが、短命に終わった。政治改革では、小選挙区比例代表並立制導入、政党助成金制度改革などが実現したが、しかし、政治不信は依然として根強く、政治改革に対する国民の期待は高まらなかった。これも現代に続いているといってよいだろう。
現代になって、1995年は、バブル経済崩壊後の長期的な経済停滞、「失われた30年」の始まりとなった年ともいえる。円高や金融機関の不良債権問題などが重なり、企業の業績悪化や失業率の増加が顕著になった。政府は、景気浮揚策を講じたが、効果は限定的だった。主要な景気浮揚策としては、公共事業投資の拡大、金融緩和、減税などが実施された。しかし、これらの政策の効果は限定的であり、経済状況は改善に向かわなかった。まさに「終わりの始まり」だった。
社会の視点から。
オウムや阪神淡路大震災がクローズアップされ、消費や文化活動が低迷した年と定義されがちだが、1995年はマイクロソフトのWindows 95が発売された。パソコンの操作がより簡単になり、インターネットの普及は、情報通信技術 (ICT) 革命の幕開けとなった。こうした下地もあり、若者文化では、オタク文化や渋谷系などマスから離れたニッチな領域でのカルチャーが芽生えるようになった。
阪神・淡路大震災では、多くのボランティアが被災地支援に駆けつけ、地域コミュニティの重要性が再認識された。この流れは、2011年の東日本大震災、今年の能登半島沖地震における市民のボランティア活動への積極的な参加の源になっているといってよいだろう。1995年は、様々な思想がぶつかり合い、新しい思想が模索された年、そして従来の価値観や思想が揺らぎ、新しい時代に対応した思想が求められたように思える。この年で印象的な出来事は、青島知事が都知事選で現職の鈴木知事を破り、「96都市博」を中止にさせたことだ。97年に都市博会場予定地に本社を移したフジテレビは、移転記念としてドラマ「踊る大捜査線」を放映する。人気ドラマとなったが、荒涼とした博覧会予定地を走りまわる刑事の名前が「青島」だったことも印象的だった。この年開通した「ゆりかもめ」線に初めて乗った際、東京都心近くに広がる広大な開発予定だった敷地の空虚な感じも忘れられない。
改めて振り返ると、携帯電話、インターネット、次世代ゲーム機、貿易/価格自由化、規制緩和、雇用柔軟化・・・。この年から始まったものが、現代社会の礎になっており、これらが次の世界のさらなる中核になりつつあることも体感できる。
昨年刊行された著者の「1973年に生まれて 団塊ジュニア世代の半世紀」も読みたくなった。
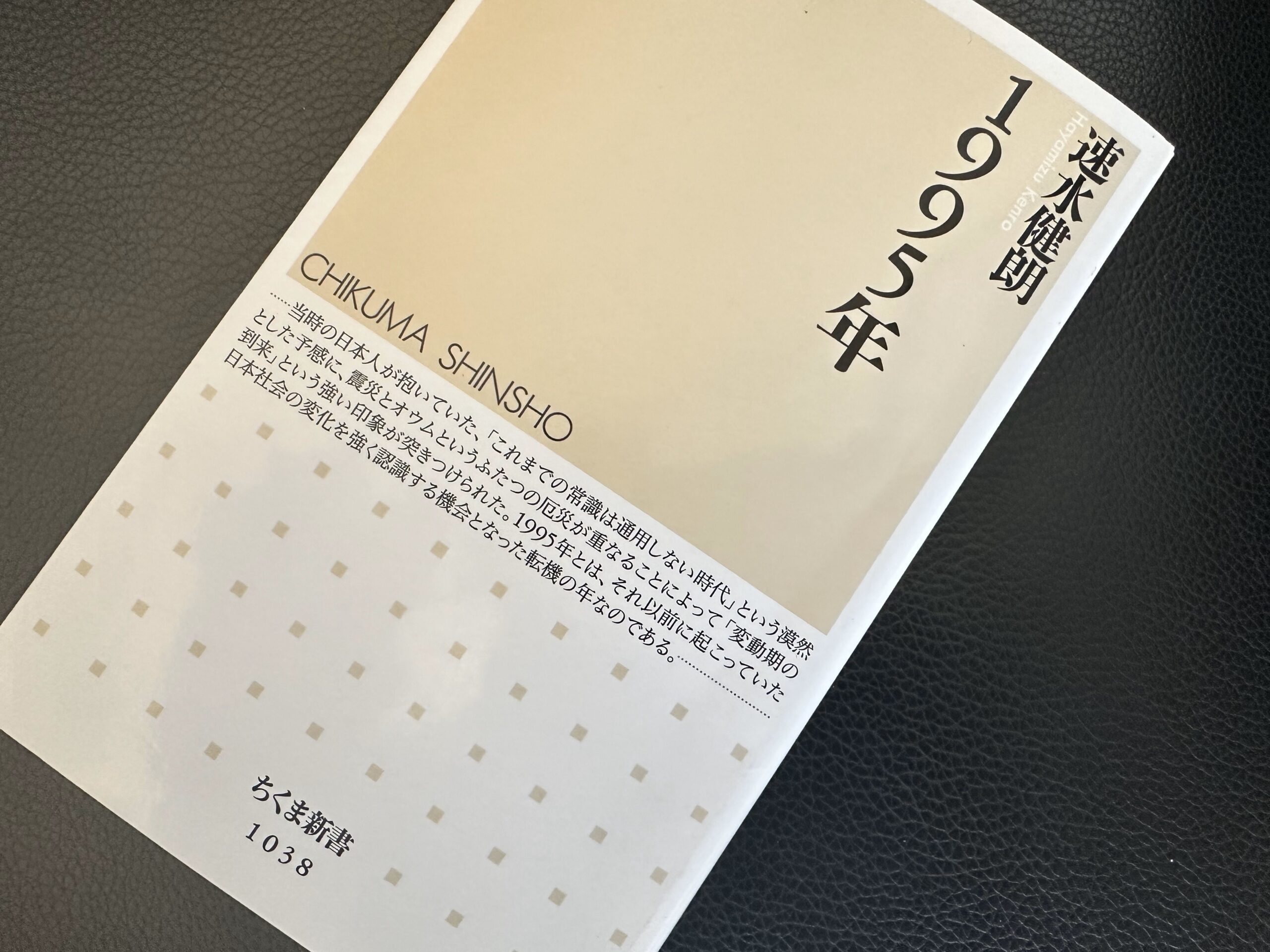

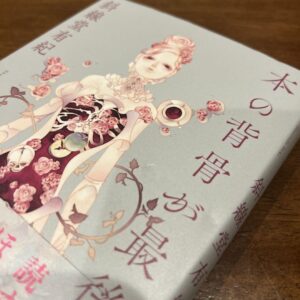

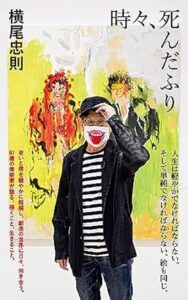
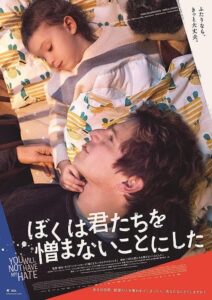
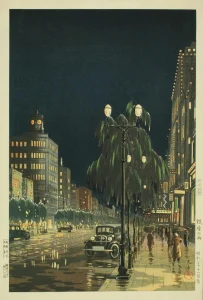
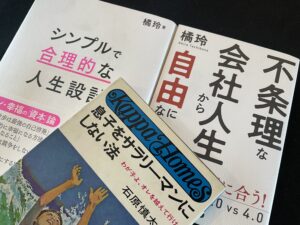
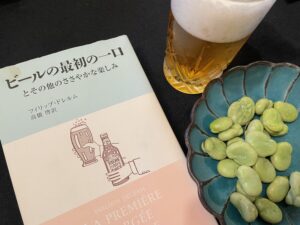
コメント